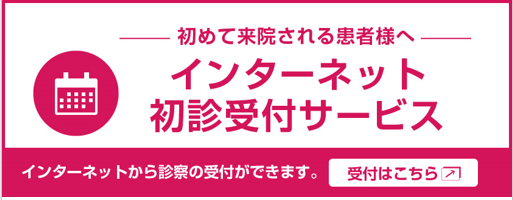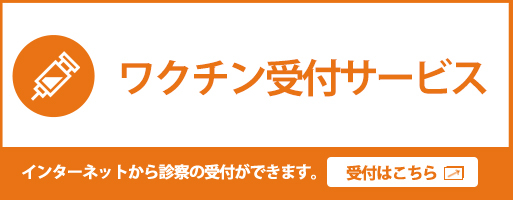漢方について
漢方薬の得意分野は?
漢方薬は1剤に複数の成分が含まれているので、複数の症状に効く場合があります。
また漢方薬のべースとなる漢方医学は、訴えや体質を重視し、漢方薬を選択します。
そのため、体質に由来する症状、検査に表れない不調などの改善を得意としています。
どのくらいの期間飲むと効果が出るの?
症状の度合いや期間の長さ、体質や生活習慣などで効果発揮には個人差があります。
1か月ぐらい服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。
なぜ漢方薬は、食前に飲むの?
食事の影響を受けにくいこと、漢方薬のこれまでの習慣や経験に基づいています。
※食前:食事の1時間から30分前(胃の中に食べ物が入っていないとき)
漢方薬は何で飲めばいいの?
コップ一杯程度のお湯または水と一緒に飲んでください。
ジュースや牛乳と飲むとそれらの成分と相互作用を示すものもあるので避けましょう。
西洋薬と漢方薬の違いは?
西洋薬は基本的に単一の有効成分で症状を絞り込んで使用するのに対し、漢方薬は複数の生薬を組み合わせることで、複数の症状に作用し改善を目指します。
熱中症・夏バテ
夏バテは、古典では注夏病(ちゅうかびょう)などと呼ばれていました。
「元気がなく身体が火照るのは、暑さにより体が傷つけられたためだ」という記載がされています。【黄帝内経素問・刺志論】
よく用いられる漢方薬は、清暑益気湯(せいしょえっきとう)、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、五苓散(ごれいさん)です。
・五苓散(ごれいさん):熱中症の症状が出始めた頃の下痢、悪心、嘔吐に。
・清暑益気湯(せいしょえっきとう):熱中症で疲弊し、ロ渇・発汗が持続している時期の食欲不振や倦怠感。
・補中益気湯(ほちゅうえっきとう):熱感、発汗、ロ渇は消退したものの、身体の疲弊が胃腸にも影響を及ぼし、夏やせ食欲不振などの症状が出るとき。
冷え症について
全身が冷える「全身型」
体内の熱産生が低下し、新陳代謝が低下。全身が冷えるタイプ。食欲不振や気力が失われ、疲労倦怠感が生じます。
【漢方薬】
体を温める生薬(乾姜(かんきょう)、附子(ぶし)、山椒(さんしょう)など)やこの補給ができる生薬(人参(にんじん)、黄耆(おうぎ)など)を含む漢方薬
・六(りっ)君子(くんし)湯(とう)、大建中(だいけんちゅう)湯(とう)、補中(ほちゅう)益(えっ)気(き)湯(とう)、八味地(はちみじ)黄丸(おうがん) など
手足が冷える「四肢末端型」
手足の先まで血液が循環しないことから手足に冷えを感じるタイプ。10代~20代女性に最も多く、疲労や無理なダイエットが背景にある可能性があります。
しもやけやたちくらみ、ニキビ、月経トラブルが起こりがちです。
【漢方薬】
血を補って身体を温まる生薬である「当帰」が含まれた漢方薬
・当帰(とうき)芍薬散(しゃくやくさん)、当帰四逆加呉茱萸(とうきしぎゃくかごしゅゆ)生姜(しょうきょう)湯(とう) など
下半身が冷える「上熱下寒型」
気や血の巡りが悪く、滞った状態で上半身がのぼせて、下半身が冷えるタイプ。顔のほてりで冷えとは気づきにくいため注意が必要です。
イライラ、頭痛、顔のほてり。肩こり。肌荒れのほか、月経トラブルや便秘が起こることもあります。
【漢方薬】
気や血を巡らせる生薬である「桂(けい)枝(し)」や「桃(とう)仁(にん)」「牡丹皮(ぼたんぴ)」などを含む漢方薬
・桂枝茯苓(けいしぶくりょう)丸(がん) など
ストレスで冷える「体感異常型」
ストレスで自律神経に影響がでて、血流が悪くなり冷えを感じるタイプ。疲れているのに眠れない、集中力がなくイライラする、食欲不振、胃痛、息が吐きづらいなどの症状がみられます。
【漢方薬】
肝の失調を調える生薬である「柴(さい)胡(こ)」を含む漢方薬
・加味逍(かみしょう)遙散(ようさん)、抑(よく)肝散(かんさん) など